2025.09.06
白内障の要因は加齢だけ?眼科医が原因から治療方法を解説

「最近視界がかすむ…」「もしかして白内障かも?」 そんな不安を感じて、白内障の原因を調べている方もいるのではないでしょうか。
白内障の主な原因は加齢ですが、実はそれだけではありません。糖尿病やアトピーなどの持病、さらには普段の生活習慣が関係していることもあります。この記事では、白内障の原因を専門医が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 白内障になる詳しい仕組み
- 加齢以外の6つの原因(糖尿病・アトピーなど)
- 今日からできる具体的な予防法
- 眼科を受診するべき症状の目安
この記事の執筆者
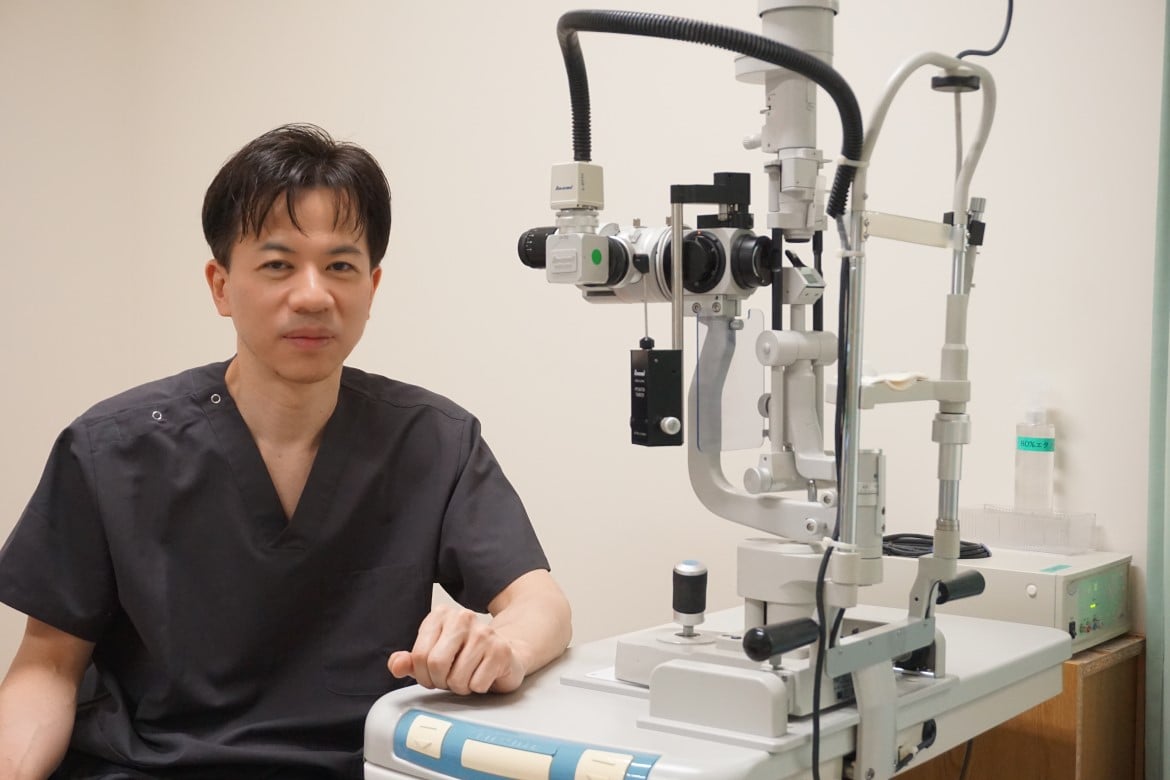
熊田充起 くまだ眼科クリニック 院長
常日頃意識しているのは、「治す眼科医療」をめざすこと。日帰りでの白内障手術を数多く手がけるほか、緑内障の早期発見や小児眼科など、幅広い患者様のニーズに対応。
目次
大前提:白内障は目の「水晶体が濁る」病気
白内障の要因を詳しく知る前に、まずは「白内障とは何か」から解説します。
私たちの目には「水晶体」と呼ばれる、カメラのレンズのような役割を持つ透明な組織があります。この水晶体は、厚みを変えることでピントを調節し、遠くや近くの物を見ることができます。
白内障とは、この水晶体が白く濁ってしまう病気です。
水晶体が濁る「タンパク質変性」
水晶体の主成分は「クリスタリン」というタンパク質と水です。若い頃、このタンパク質は規則正しく並んでいるため、水晶体は透明です。しかし、加齢や長年の紫外線の影響、その他の要因によってタンパク質が変性し、白く濁ってしまうのです。
この変化は、透明な生卵の白身に熱を加えると、白く固まってゆで卵になる様子と似ています。一度濁ってしまった水晶体は、残念ながら自然に元の透明な状態に戻ることはありません。
水晶体が濁ると光がうまく通過できなくなり、網膜に鮮明な像を結べなくなります。その結果、「視界がかすむ」「物がぼやけて見える」といった症状が現れるのです。
白内障が起こる主な原因
白内障は、特定の誰かだけがかかる珍しい病気ではありません。以下の特徴に当てはまる方は、白内障になるリスクが高い、あるいはすでに発症している可能性があります。
- 高齢の方(特に50代以上)
- 糖尿病の持病がある方
- アトピー性皮膚炎を患っている方
- ステロイド薬を長期間使用している方
- 過去に目に怪我をしたことがある方
- 紫外線を浴びる機会が多い生活を送っている方
- 喫煙習慣のある方
- 強度近視の方
詳しくは後述しますが、ご自身やご家族に当てはまる項目がないか確認してみてください。
最大の要因は「加齢」

白内障を引き起こす様々な要因の中で、最も大きなものが「加齢」です。これは年齢を重ねれば誰の目にも起こりうる、いわば自然な変化なのです。
80歳以上では「ほぼ100%が発症する」と言われている
白内障は決して珍しい病気ではありません。
厚生労働省の研究報告によると、早い人では40代から発症し、50代で約半数、60代で約7割、70代では9割以上の人に白内障による水晶体の濁りが見られます。そして、80歳を超えると、ほぼ100%の人に白内障が認められるのです。
このデータが示すように、白内障は長生きをすれば誰もが経験しうる、非常に身近な目の変化です。「自分だけがおかしいのでは?」と不安になる必要はまったくありません。
参考:『白内障とは|眼科医監修白内障LAB』
白内障の要因は「酸化」と「紫外線」
では、なぜ年齢を重ねると水晶体は濁ってしまうのでしょうか。私たちの肌にシミやシワが増えるのと同じように、目も長年にわたって様々な影響を受け続けます。その最大の要因が「酸化ストレス」です。
私たちは呼吸によって酸素を取り込んでいますが、その過程で一部が「活性酸素」という物質に変化します。この活性酸素は、細胞を傷つけ、老化を促進させる原因となります。若い頃は、体内に備わった抗酸化力で活性酸素のダメージを修復できます。しかし、年齢とともにその力は衰え、修復が追いつかなくなります。
さらに、生涯にわたって浴び続ける紫外線のダメージも水晶体内に蓄積され、活性酸素の発生を促します。こうして数十年の歳月をかけて、水晶体のタンパク質はゆっくりと変性し、濁りを生じていくのです。
若くても要注意|加齢以外の6つの原因
とはいえ、白内障は高齢者だけの病気ではありません。
特定の病気や生活習慣が、発症の引き金になったり、進行を早めたりすることがあります。ご自身の生活習慣や持病が関係していないか確認してみてください。ここでは、加齢以外の代表的な6つの原因を一つずつ詳しく解説していきます。
原因1. 糖尿病による高血糖(リスクは約5倍)
糖尿病をお持ちの方は、そうではない方に比べて約5倍も白内障になりやすいというデータがあります。
血糖値が高い状態が長く続くと、血液中の糖分が水晶体の中に「ソルビトール」という物質として蓄積されます。このソルビトールが水晶体の中に水分を引き込んでしまうため、水晶体がむくんで濁りやすくなるのです。特に血糖コントロールが良くない場合、進行が速いのが特徴で、40代といった若い年代でも白内障が進んでしまうことがあります。
糖尿病の治療をきちんと続けることが、目の健康を守ることにも直結するのです。
参考:『白内障と疫学研究|日本白内障学会』
原因2. アトピー性皮膚炎
意外に思われるかもしれませんが、若年性白内障の原因として最も多いのがアトピー性皮膚炎です。アトピーを持つ方の中には、20代や30代で手術が必要になるほど進行するケースも珍しくありません。
はっきりとしたメカニズムはまだ解明されていませんが、目の周りの皮膚炎による炎症や、かゆみで強く目をこすってしまう物理的な刺激が、水晶体にダメージを与えていると考えられています。
アトピー性白内障は、加齢による白内障よりも進行が速い傾向があるため、アトピー性皮膚炎をお持ちの方で「最近見えにくいな」と感じたら、年齢に関わらず一度眼科で相談することをおすすめします。
原因3. ステロイド薬の長期使用
実は喘息の治療で使われる吸入薬や、自己免疫疾患の治療で使われる内服薬など、ステロイド薬を長期間使用している場合、その副作用として白内障が起こることがあります。これを「ステロイド性白内障」と呼びます。
ステロイドは水晶体のタンパク質の代謝に影響を与え、特に水晶体の後ろ側(後嚢)から濁りが生じやすいのが特徴です。一度発症すると、数ヶ月から1年程度で手術が必要になるほど進行が速いことが知られています。
治療のためにステロイドが欠かせない方は、定期的に眼科検診を受け、目の状態をチェックしておくことが大切です。
原因4. 事故やケガによる「目の外傷」
スポーツ中にボールが目に強く当たったり、転倒して目をぶつけたりすると、目に強い衝撃が加わることも白内障の原因となります。これを「外傷性白内障」と呼びます。
強い衝撃で水晶体を包んでいる袋(嚢)が傷つくと、そこから濁りが広がっていきます。怪我をした直後だけでなく、数年経ってから徐々に進行してくるケースもあります。若い方でも、スポーツや事故が原因で片目だけ白内障になることは決して珍しくありません。
目に怪我をした経験がある方は、のちに視力の変化を感じたら眼科を受診しましょう。
原因5. 生まれつき(先天性白内障)
非常に稀ではありますが、生まれつき水晶体が濁っている「先天性白内障」の赤ちゃんもいます。
これは、お母さんのお腹の中にいる間に、風疹ウイルスなどに感染することが主な原因とされています。遺伝が関係する場合もあります。
赤ちゃんの黒目の中心が白っぽく見えたり、視線が合わないといった様子が見られたら、先天性白内障の可能性があります。この場合、視力の発達を妨げないように、生後なるべく早い時期に手術が必要となります。
原因6. その他の要因(喫煙・強度近視など)
上記のほかにも、以下のような生活習慣や目の状態が、白内障のリスクを高めることが分かっています。
喫煙
タバコを吸うと、白内障の原因となる「活性酸素」が大量に発生します。また、活性酸素から体を守るビタミンCなどの抗酸化物質も破壊されてしまうため、喫煙者は非喫煙者に比べて白内障のリスクが高まります。
強度近視
近視の度が非常に強い「強度近視」の方も、白内障の発症が早い傾向にあります。ある研究では、強度近視の人はそうではない人と比較して、白内障になる確率が5倍以上高かったという報告もあります。
これらの要因は、複数重なることで、さらにリスクを高める可能性があります。ご自身の生活を振り返り、思い当たる点があれば、次の予防・対策のセクションを参考にしてください。
白内障の予防と進行を遅らせるための対策

白内障の様々な原因を知ると「何とか進行を遅らせることはできないのか?」と思うかもしれません。残念ながら、一度濁ってしまった水晶体を薬で元に戻すことはできませんが、その進行スピードを緩やかにするために、私たちが今日から実践できる対策はあります。
ここでは、その具体的な方法をご紹介します。
【紫外線対策】UVカットのサングラスや帽子を習慣に
白内障の発症・進行を早める最大の環境要因は紫外線です。そのため、日常的に紫外線から目を守ることが、最も効果的な予防策の一つとなります。
具体的な対策として、屋外に出る際はUVカット機能のあるサングラスや帽子を着用する習慣をつけましょう。サングラスを選ぶ際のポイントは、レンズの色の濃さではなく、紫外線(UV)をどれだけカットできるかです。「UV400」や「紫外線カット率99%以上」といった表示のあるものを選びましょう。色が濃すぎるレンズは、かえって瞳孔が開いて多くの紫外線を取り込んでしまうことがあるため、注意が必要です。
また、紫外線は正面からだけでなく、様々な角度から目に入ってきます。つばの広い帽子やサンバイザーを併用することで、より効果的に目を守ることができます。
【食生活の改善】抗酸化作用のある栄養素を意識する
白内障の進行には、活性酸素による体の「サビ」が関係しています。そのため、抗酸化作用を持つ栄養素を食事から積極的に摂り、体の内側から酸化ストレスを和らげることが有効です。
特に意識して摂りたい栄養素は以下の通りです。
ビタミンC
レモンやイチゴなどの果物、パプリカなどの野菜に豊富です。強力な抗酸化作用で水晶体を守ります。
ビタミンE
アーモンドなどのナッツ類や、植物油に多く含まれています。
特定のサプリメントに頼るのではなく、様々な色の野菜や果物をバランス良く取り入れた食生活を心がけることが、目の健康に繋がります。
ルテイン、ゼアキサンチン
ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれ、有害な光から目を守るフィルターのような働きをします。
【禁煙】喫煙は白内障の大きなリスク因子
白内障に限った話ではありませんが、喫煙は百害あって一利なしと言われています。多くの研究で、タバコを吸う人は吸わない人に比べて、白内障の発症リスクが高まることが証明されています。
タバコを吸うと、体内で大量の活性酸素が発生するだけでなく、水晶体を酸化から守るビタミンCなどの貴重な栄養素が大量に消費されてしまいます。さらに、ニコチンの作用で血流が悪くなることも、水晶体の健康に悪影響を及ぼします。
朗報なのは、禁煙をすれば、将来の白内障リスクを確実に下げられるということです。「もう歳だから…」と諦めずに、ご自身の目の健康のため、そして全身の健康のために、禁煙することを推奨しています。
受診の目安は?症状のセルフチェックと初診の流れ
ご自身の白内障の原因や予防法について理解が深まったところで、最後に「専門医への相談」という具体的なステップについても解説していきます。
「どんな症状があれば受診すべき?」「病院では何をするの?」といった、多くの方が抱く疑問に回答します。
これって白内障?症状セルフチェックリスト
以下に挙げる症状にもし複数当てはまるようであれば、白内障が始まっている可能性があります。
- 視界が全体的にかすんで見える
- 太陽の光や車のライトが以前よりまぶしく感じる
- 物が二重、三重にだぶって見える
- 明るい場所より、薄暗い場所の方が見えやすい
- 白っぽいものが、少し黄色がかって見える
- 眼鏡やコンタクトの度が、すぐに合わなくなる
これらの症状は、白内障の代表的なサインです。「きっと歳のせいだろう」と自己判断で放置せず、一度専門医に相談してみることをお勧めします。
受診タイミングは「視力に違和感を感じたら」
では、具体的にいつ眼科を受診すればよいのでしょうか。結論「視力に関わらず、ご自身が見えにくさによって日常生活に不便を感じ始めたとき」が、受診を検討すべきタイミングです。
例えば、以下のようなシチュエーションがあれば眼科の受診を推奨しています。
- 車の運転中、標識や信号が見えにくい
- 階段の上り下りで、足元が不安に感じる
- 新聞や本の文字が読みにくく、趣味を楽しめない
- 人の顔がぼんやりして、見分けにくい
白内障は、放置して自然に治る病気ではありません。見えにくさを我慢していると、知らず知らずのうちに行動範囲が狭まったり、転倒などの思わぬ事故に繋がったりする可能性もあります。少しでも目に違和感を感じたら、気軽に受診してください。
まとめ:「自分には関係ない」と思わず、まずは早期受診が大切
本記事では、白内障の要因について、加齢から糖尿病、アトピー、生活習慣に至るまで網羅的に解説してきました。
白内障は誰にでも起こりうる自然な変化ですが、その原因は一つではなく、様々な要因が絡み合っていることをご理解いただけたかと思います。大切なのは、いたずらに不安がるのではなく、原因を正しく知り、ご自身の目と向き合うことです。
この記事のポイント
- 白内障の最大の要因は加齢であり、誰にでも起こりうる
- 糖尿病やアトピー、ステロイド薬の使用も原因となりうる
- 紫外線対策や禁煙、バランスの取れた食事が進行予防に繋がる
- 「生活での見えにくさ」が眼科受診のサイン
当院くまだ眼科クリニックでは、これまでの1万件以上の白内障診断・手術の知見を踏まえて、まずは痛みなく初診を行います。『自分にはまだ関係ない…』と思わず一度眼科に受診いただければと思います。
「白内障」の関連記事
「軽度な白内障」の症状は?見え方 や最適な治療方法について解説!
更新日:2025.02.26
【単焦点・多焦点の違い】白内障眼内レンズの特徴について院長が分かりやすく解説
更新日:2025.11.03
【合併症について】白内障手術後も「診察を行う理由」について院長が解説
更新日:2025.11.03
